ハロー、こんばんは、GONZAです!
💡 この記事はこんな方におすすめ!
- 疲れやすくてエネルギー不足を感じている方
- 甲状腺ホルモンのバランスが気になる方
- 集中力や記憶力が最近落ちてきたと感じる方
- 妊娠・授乳中で栄養を気にしている方
- サプリメントの正しい摂り方を知りたい方
皆さんは、【ヨウ素】についてどれくらい知っていますか?
今回は、【ヨウ素】について詳しく解説していきます!
ヨウ素とは?
ヨウ素(英語:Iodine)は、体内で微量しか存在しない「必須微量ミネラル」のひとつで、甲状腺ホルモン(T3・T4)をつくる材料となります。
これらのホルモンは、代謝、成長、神経機能に深く関わっており、健康維持に欠かせない存在です。
成人の体内には約20~50mgのヨウ素が存在し、そのほとんどが甲状腺に蓄えられています。
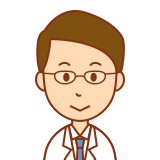
ヨウ素の働き(補足)
甲状腺ホルモン(T3・T4)には以下のような働きがあります:
・基礎代謝の調整
・体温の維持
・筋肉・心臓・脳・神経の正常な機能維持
・発達・成長・脂質代謝の調整
つまり、ヨウ素は「体全体のエネルギーと成長の指揮者」と言える存在です。
ヨウ素の主な役割
✅ 甲状腺ホルモンの材料
T3(トリヨードサイロニン)やT4(サイロキシン)といった甲状腺ホルモンは、すべてヨウ素を含んでおり、基礎代謝・体温調節・エネルギー産生に重要な役割を果たします。
✅ 成長と発達のサポート
特に胎児や乳幼児期にはヨウ素が不足すると、発育障害や知的発達遅延の原因になることもあるため、妊婦・授乳婦の摂取がとても大切です。
✅ 脳機能の維持
ヨウ素不足により、注意力・記憶力の低下や気分の落ち込みが見られることも。
🔍 補足:ヨウ素不足による主な症状
| 症状 | 主な影響 |
|---|---|
| 甲状腺腫(バセドウ病・橋本病) | 甲状腺が腫れて代謝異常を引き起こす |
| 疲労感・無気力 | エネルギー代謝の低下 |
| 寒がり・体温低下 | 基礎代謝の低下 |
| 発育・知能障害(小児) | 脳・神経の発達不全 |
ヨウ素を多く含む食品
| 食品名 | ヨウ素含有量(μg/100g) |
| 昆布(乾燥) | 2000〜2500μg |
| 干しひじき | 約700μg |
| わかめ(生) | 約100〜300μg |
| 焼きのり | 約190μg |
| たら(魚) | 約120μg |
| 卵黄 | 約50μg |
| 牛乳 | 約20〜30μg |
※昆布のヨウ素含有量は非常に高いため、摂取量に注意しましょう。
✅ 1日の推奨採取量
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より。
| 性別・年齢 | 推奨量(μg/日) | 耐容上限量(μg/日) |
| 男性(18~64歳) | 130μg | 3000μg |
| 女性(18~64歳) | 130μg | 3000μg |
| 妊婦 | 140μg | 3000μg |
| 授乳婦 | 210μg | 3000μg |
ヨウ素の過剰採取の注意点
| 症状 | 内容 |
| 甲状腺機能低下 | 甲状腺ホルモンの分泌が抑制される |
| 甲状腺腫 | 甲状腺が腫れる、のどに違和感 |
| 動悸・発汗異常 | ホルモンバランスの乱れ |
ヨウ素と他栄養素との相互作用
ヨウ素は、セレン、鉄、亜鉛、ビタミンAなどと一緒に摂ることで効果が高まります。
- セレン:甲状腺ホルモンの活性化に必要。
- 鉄:ホルモン合成に関与。鉄不足はヨウ素の働きを低下させる。
- ビタミンA・亜鉛:甲状腺受容体の感受性に関与。
📌ヨウ素を効率よく採るには
- わかめ・昆布などを毎日の味噌汁やスープに取り入れる
- サプリメントは表示された量を守って摂取
- ヨウ素が豊富な食品を常食している場合、サプリと合わせすぎない
- 海藻が苦手な方はサプリでの補助も検討
日本でヨウ素サプリがあまり知られていない理由
多くの方が中学校の理科の授業で「ヨウ素液をデンプン検出に使う実験」を経験したと思います。
そのため、「ヨウ素=化学実験で使う薬品」といった印象を持ってしまい、「栄養素」としてのヨウ素を意識しにくいという側面もあります。
1. 日本人の食文化では海藻摂取量が非常に多い
日常的に昆布・わかめ・ひじきなどを食べる習慣があるため、自然にヨウ素が摂取できている人が多く、サプリの必要性があまり意識されません。
2. 過剰摂取リスクが現実的にある
食事からの摂取で推奨量を超えるケースもあるため、追加のサプリ使用には注意が必要とされています。
3. 甲状腺疾患を持つ人が多い国
バセドウ病・橋本病など、ヨウ素と関係のある疾患の患者が多いため、自己判断での摂取に医療的なリスクが伴うとされます。
4. 海外と栄養環境が異なる
アメリカ・ヨーロッパなど海藻を食べない地域ではヨウ素不足が深刻であり、ヨウ素塩やサプリの活用が進んでいます。日本ではその必要性が少ないため、認知が広がっていません。
補足:理科のヨウ素液と栄養素のヨウ素の違い
中学校の理科で使う「ヨウ素液」は、デンプンに反応して青紫色に変化する試薬ですが、これは医薬品グレードのヨウ素(I₂)とヨウ化カリウム(KI)の混合液です。
一方で、食品やサプリに含まれるヨウ素は、主にヨウ素イオン(I⁻)の形で、体に必要な必須ミネラルです。
| 比較項目 | ヨウ素液(理科) | 栄養素のヨウ素 |
|---|---|---|
| 主な形 | I₂(分子ヨウ素)+KI | I⁻(ヨウ素イオン) |
| 用途 | デンプン検出用の試薬 | 甲状腺ホルモンの材料 |
| 飲用の可否 | 飲用不可(有毒の場合あり) | 適量なら摂取が必要 |
同じ「ヨウ素」という名前でも、使い方・安全性・効果はまったく異なります。
ヨウ素サプリメントの活用と注意
○効果的な理由
- 食生活で摂りづらい人の栄養補助
- 妊娠中・授乳期など、必要量が増す時期のサポート
- 海藻を避けている方(甲状腺疾患や食事制限)にも有効
○注意点
- 過剰摂取を避ける(1日3000μgを超えない)
- 甲状腺に疾患がある方は、医師に必ず相談を
- 他のサプリとの併用による総摂取量の確認
まとめ
ヨウ素は、甲状腺ホルモンの生成やエネルギー代謝、成長や発達に欠かせない重要なミネラルです。 日常的に海藻類を食べることで自然に補えますが、摂りすぎには注意が必要です。
食事が偏りがちな方や妊娠・授乳中の方は、サプリメントを活用しながら、バランスよくヨウ素を摂取しましょう。
それでは、また次回のブログでお会いしましょう!
引用・参考文献
- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
- 日本栄養士会「ヨウ素の働き」
- 米国NIH「Iodine – Fact Sheet for Health Professionals」
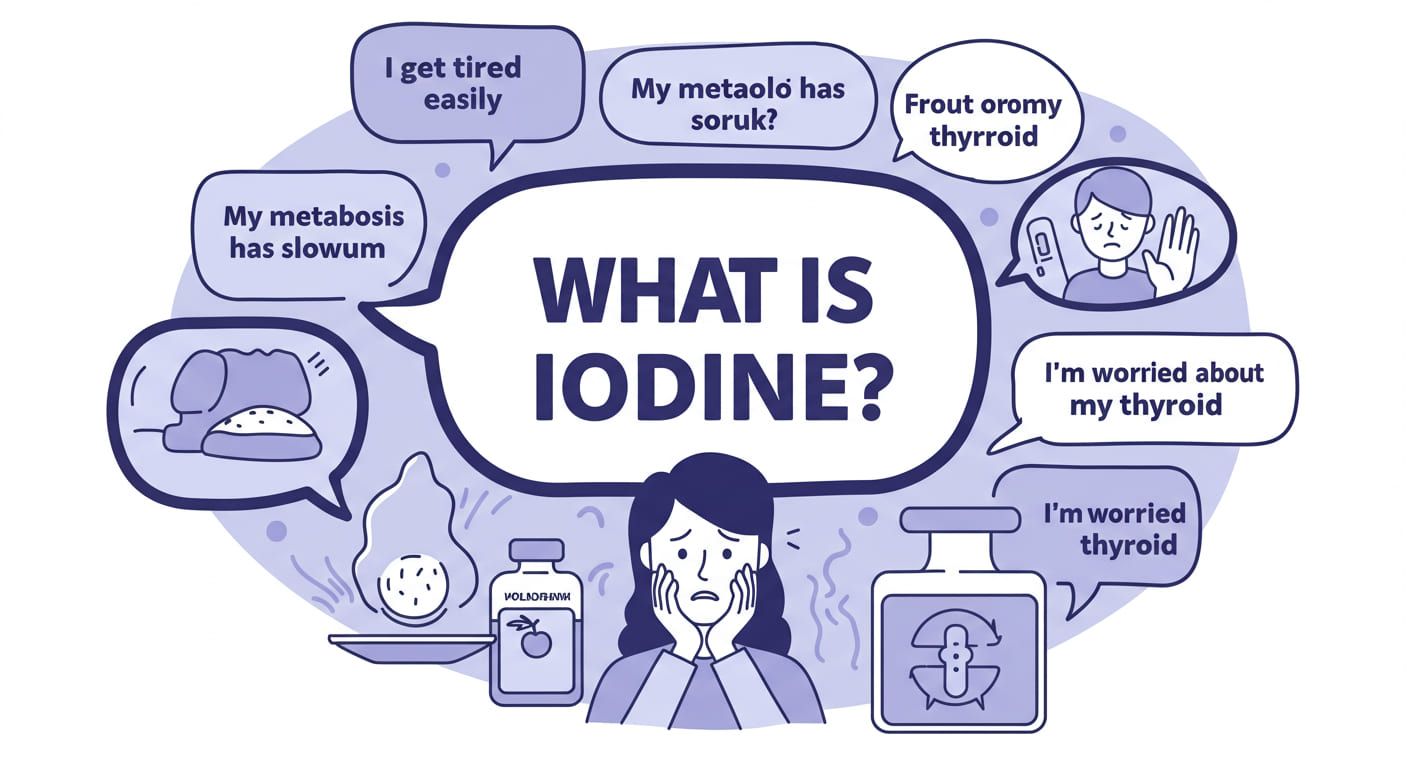

コメント